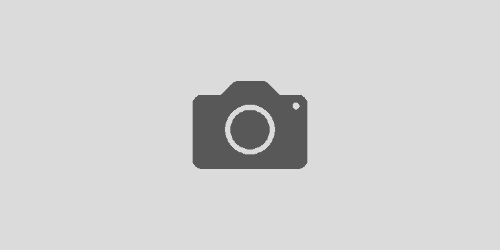「自分の頭で考える」とはどういうことか。因数分解して考えてみた。

前回の記事で、「読書は自分の考えを広げたり、深めたりするためにするものだ」と書きましたが、そういえば、読書を習慣にし始めた頃の自分は、「自分で考える」について理解できていなかった、と思い出し、この記事を書くに至りました。
「自分で考えろ」「もっと考えろ」・・こんな事を言われても、言われる本人からしたら、「え、自分は考えているんだけど・・」という認識のことも多いはずです。
僕は、「考えなしな奴」と思われるほど、周りのレベルから遅れている訳ではなかったようですが、それでも、「自分の頭で考える」をしっかり理解し始めたのが、ここ2〜3年(現在、28歳です)です。
「自分で考える」事を、もっと早くにできていたらなぁ・・と後悔をしています。
そこで、今、「自分の頭で考える」に悩んでいる人に、何かしらの気づきを提供できれば、と思い、この記事を書きました。
「自分の頭で考える」の前提
まず、この「自分の頭で考える」について、いくつか注意点、あるいは前提を挙げておきます。
- 「自分の頭」で考えるからと言って、他人と違う結論を導かなくても良い
- 「考える」は無意識下では行えない
一つ目はマインドセットの面の前提で、「自分の頭で考える」の「自分の頭」を意識しすぎるがために見過ごされがちなポイントだと個人的には思います。
仮に、考えて導いた結論が大多数の人と同じだったとしても、自分の頭で考えていないわけではない、と言うことです。
結果のクリエティビティよりも、自分で考えた過程が重要、とも言い換えられるかもしれません。
二つ目は実践における注意点ですが、「考える」は、無意識では行えません。「1日中考えたんだけど、いい案は思い浮かばなかった」場合、「考えた」を動詞に用いるのは誤っています。
この場合、「悩んでしまった」とか「集中できなかった」とか、そういう動詞が使われるべきだと感じます。また、この混同が、「考える」をわからなくさせているのだとも感じます。
「自分の頭で考える」とは
まず、結論を示しておきます。「自分の頭で考える」というのは、以下の要素の掛け算で表せます。