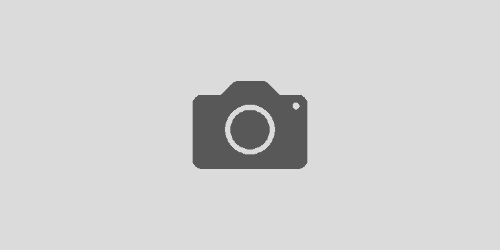セブンイレブンを競合と比較 セブンは何がすごいのか

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン・・
好みは人それぞれですが、「どのコンビニがすごいか?」と聞かれれば、だいたいの人は、「セブンイレブン」と答えるでしょう。
では、セブンイレブンは、どのようにすごいのか。なぜすごいのか。これについて、答えを持ち合わせているでしょうか。
今回は、なんとなく思われている、「セブンイレブンのすごさ」について、調査し、まとめました。
まずは、直近の業績を見てみましょう。
「セブンイレブンはすごい」は気のせいではない

セブンイレブンは、店舗数、売上高ともに業界1位です。しかも、1店舗あたりの売上高が競合2社に比べて高いため、生産性が高いコンビニであると言えます。
それでは、この内訳を・・と思いましたが、今回、これがなかなか捉えられませんでした。
はじめは、これまでやってきたように、財政状態の違いから差別化の源泉を見つけ出そうと考えていました。
しかし、設備投資額に特徴があるわけでもなく、以前分析したスタバやZARA(INDITEX社)のように、投資の選択・集中による差別化が、コンビニ業界では行われていないようでした。
それでは、どのように「セブンイレブンのすごさ」を捉えれば良いのでしょうか。
セブンイレブンのすごさ=・・・
今回、コンビニの大手3社を比べてみて感じたことは、「程度の差はあれ、どこも似たようなことをやっている」ことです。
業界で商売を行ってゆくための基礎・基本がどこでも行われており、日々、営業が行われているようです。
ですから、投資方針・運営方式の違い、ネットワークづくりなど、他の業界において個性が出やすい(とはいえ、勇気は必要ですが)リソース配分に、差別化の源泉が見られないことには悩まされました。
コンビニに限らず、小売業はそうなのかもしれません。商品を自社で秘密裏に研究開発するわけではなく、メーカー、商品の製造地、成分表示、すべてが競合に対して明るみに出てしまう小売業では、他の業界のような経営資源の配分によるポジショニングアプローチが難しいのかもしれません。
では、「セブンイレブンはすごい」と思う、この体感は、どこからくるのでしょう。これを僕は、今回、以下の因数分解で明らかにしようと試みました。
セブンイレブンのすごさ = 選好 × 認知 × 配荷
この因数分解、ご覧になったことがある方もみえるかもしれません。「確率思考の戦略論」の中で、森岡毅さんと今西聖貴さんが用いておられた「売上=プレファレンス(選好)×認知×配荷」から引用したものです。
「選好」とは好みのことです。
また、「配荷」とは、流通量のことです。換言すると、「あるものを欲しいとき、それを買いやすい度合い」でもあります。
「確率思考の戦略論」では、消費行動の確率分布から各社(・ブランド)の売上高が予測できること、あるいは、ある売上を達成するために必要な認知度と配荷の量を事前に予測し、それをマーケティングに活用できることが、例をもとに書かれていました。
その際の事例の商材はシャンプーでしたが、その確率分布の構造は、前提条件的にコンビニにも適用して差し支えないと考えられます。この方程式は、小売業の競争市場と相性が良いと感じます。
ゆえに、今回は、この考え方に基づいて、細かく要素を比較してゆきます。